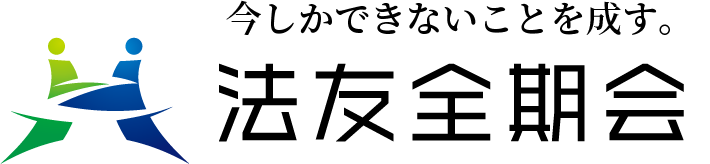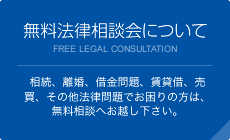法友全期会会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は法友全期会と称する。
第2条(事務所)
本会は事務所を代表幹事の事務所に置く。
第3条(目的)
本会は、法友会に所属する新進弁護士の相互研鑚と親睦を図るとともに、司法制度の民主的発展及び弁護士業務拡充のための諸活動を通じて法友会、東京弁護士会並びに日本弁護士連合会の運営に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会はその目的達成のため次の事業を行う。
1.司法制度の発展のための調査研究
2.東京弁護士会及び日本弁護士連合会の会務に関する調査研究
3.弁護士業務拡充のための調査研究
4.各種研究会・懇談会・研修会等の開催
5.機関誌等の発行
6.出版、講演等の収益事業
7.その他目的達成のために必要な事業
第2章 会員
第5条(会員資格)
本会は司法修習終了後15年に達した日の翌日以後における最初の4月1日を迎えていない弁護士であって、法友会に所属する者をもって会員とする。
第3章 組織及び機関
第6条(総会)
総会は定時総会と臨時総会とする。定時総会は毎年3月に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
第7条(総会の審議事項)
総会は下記の事項を審議する。
1.代表幹事の選任
2.監事の選任
3.会則の改正、規則の制定・改廃
4.予算・決算の承認
5.その他執行部会が総会に付議するを相当と認めた事項
第8条(招集・議長)
総会は代表幹事が招集する。
総会の議長は総会で選任する。
議長が選任されるまでは代表幹事が仮に議長となる。
第9条(議決)
総会の議決はこの会則に特別の定めがある場合を除き出席会員の過半数によるものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
総会の議長は会員として議決に加わることができない。
第10条(役員)
本会に次の役員を置く。
1.代表幹事:1名
2.副代表幹事:若干名
3.政策委員会、業務委員会、企画委員会、その他総会又は執行部会の議を経て置かれた委員会の委員長(以下「各委員会の委員長」という。):各1名
4.監事:1名
副代表幹事は会員中から代表幹事が選任する。
第11条(役員の権限)
代表幹事は本会を代表し会務を掌理する。
代表幹事は副代表幹事の中から1人又は複数の職務代行者を指名し、必要に応じて代表幹事の職務を代行させることができる。
副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があるときは、前項の規定に関わらず副代表幹事の互選により選出された者が代表幹事の職務を代行する。
各委員会の委員長は、各委員会の事務を掌理する。
監事は本会の会計の監査を行い、総会において監査報告をする。
第12条(事務局)
代表幹事は事務局を設けて本会の事務を処理させる。
事務局は事務局長1名、事務局幹事若干名によって構成する。
事務局長は副代表幹事の中から、また事務局幹事は会員の中から代表幹事が選任する。
第13条(執行部会)
本会に執行部会を置く。
執行部会は次に掲げる者をもって構成する。
1.代表幹事
2.副代表幹事
3.事務局幹事
4.各委員会の委員長
第14条(幹事の任期)
執行部会を構成する各幹事の任期は選任された年の4月1日から翌年の3月末日までとする。ただし、任期が満了しても後任の幹事が選任されるまではその職務を行う。
第15条(執行部会の審議事項)
執行部会は次の事項を審議する。
1.総会に付議する事項
2.本会の常務に関する事項
3.その他代表幹事が執行部会に付議するを相当と認めた事項
第16条(執行部会の運営)
執行部会は代表幹事が招集する。
執行部会は代表幹事が議長となる。
執行部会の議決については第9条の規定を準用する。
執行部会は全会員に開かれた審議に努める。
執行部会は審議の必要上、第13条第2項各号に掲げる者以外の者の意見を徴することが適当であると認めるときは、これらの者に対し執行部会への出席を求めることができる。ただし、この場合、第13条第2項各号に掲げる者以外の者は意見を述べることはできるが、決議に参加することはできない。
第17条(委員会)
本会の目的達成のため次の委員会を置く。
1.政策委員会
2.業務委員会
3.企画委員会
第18条(委員会の設置)
本会は必要に応じ総会又は執行部会の議を経て、特定の事項を行うためその組織及び権限を定めてその他の委員会を置くことができる。
第19条(委員会の運営)
委員会は委員長1名、委員若干名にて構成し、委員長及び委員は会員の中から代表幹事が選任する。
委員会の委員長及び委員の任期は別に定める場合を除き第14条を準用する。
第20条(監事の任期)
1.監事の任期は別に定める場合を除き第14条を準用する。
第21条(会員集会)
代表幹事は、広く会員の意見を聴取する必要があると認める場合又は広く会員に報告すべき重要な事項があると認める場合、全会員に出席を促して、会員集会を開催することができる。
会員集会は、代表幹事が議長となる。
出席会員は、会員集会において意見を述べ、決議に参加することができる。
第4章 会計
第22条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの1年とする。
第23条(会費)
本会の会員は会費を納入する。
会費の金額については毎年総会において定める。
本会は会員以外からの賛助会費を受けることができる。
出産した会員(以下「出産会員」という。)より申出があったときは、出産日の属する年度の翌年度の会費を免除する。出産会員は、会費免除の申請を出産日の属する年度の翌年度内に行わなければ、その権利を失う。
出産会員の他、総会において定めた場合には当該総会決議日が属する年度の会費を免除することができる。
第24条(収益事業)
会計年度は、本会の会計年度(毎年4月1日から翌年3月末日までの1年)と同一とする。
申告の納税地は、東京都千代田区霞が関一丁目1番3号所在の弁護士会館内とする。
申告書への署名・押印及び納税は、申告期限(毎年5月)現在の代表幹事が行う。
会計年度終了時における剰余金については、翌会計年度に繰り越す。
会計帳簿及び帳票類(印税通知書・領収書・預金通帳等)については、代表幹事が次期代表幹事に引き継ぎ、各年度の代表幹事は責任を持って申告期限から10年間保存する。
出版、講演等の収益事業に係る権利は、本会に帰属する。
第5章 会則改正
第25条(会則改正)
本会則を改正するには会員が50名以上出席した総会でその3分の2以上の同意を要する。
附則
本会則は昭和60年4月1日より施行する。
・平成19年3月9日第13条改正施行
・平成19年8月17日改正施行
・平成22年3月12日改正 第9条から第20条までの改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
・平成23年12月2日改正施行
・平成24年5月25日改定施行
・平成26年3月7日改定 第5条の改定規定は、平成27年10月1日から施行する。
・令和6年3月7日改定 第23条の改定規定は、令和6年4月1日から施行する。